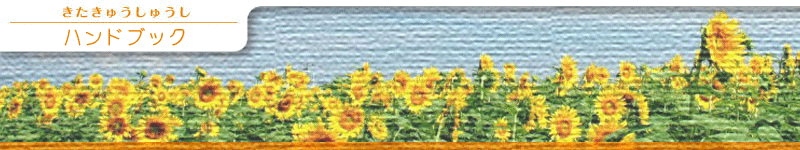
盲ろう者のコミュニケーションについて
Ⅰ.はじめに
私たちは無意識のうちに、日常生活に必要な多くの情報を視覚と聴覚から得ています。この情報を得ることで、地域社会での生活や人との出会い・交流など、自らの生活を創り上げています。
視覚・聴覚に障害があり、必要な情報を得ることが難しい状態は、情報障害とも言われています。
ここでは、この視覚・聴覚の両方に障害がある「盲ろう者」のコミュニケーションについて社会資源をご紹介します。
Ⅱ.「盲ろう」の定義
「盲ろう」という障害名は法的に定義づけられているものではなく、一般的に呼称されているものですが、近年行政文書等の中にも普通に使われるようになってきています。
「盲ろう」という表現が初めて使われたのは、1981年筑波大学附属盲学校の盲ろうの生徒、福島智さんの大学進学を支援するために「福島智君とともにあゆむ会」が作られた時です。
Ⅲ.盲ろうの種類とコミュニケーション
一口に盲ろうといってもいろいろなタイプがあります。一般的には次の4種に大別されます。
・全盲ろう:まったく見えなくてまったく聞こえない。
・全盲難聴:まったく見えなくて少し聞こえる。
・弱視ろう:少し見えてまったく聞こえない。
・弱視難聴:少し見えて少し聞こえる。
ちなみに“重度盲ろう者”とは・・・
全国盲ろう者協会では、視覚障害、聴覚障害ともに1級〜2級の範囲の人を「重度盲ろう者」と呼んでいます。しかし、法的に位置づけられたものではありません。
1.「盲ベース」と「ろうベース」とは
盲ろう者のうち、視覚障害が先に発症して、聴覚障害が後に発症した人を「盲ベースの盲ろう者」、逆の場合、聴覚障害が先に発症して、視覚障害が後に発症した人を「ろうベースの盲ろう者」と呼称して区別する場合があります。おおむね、「盲ベース」で盲学校教育を受けた人は点字がコミュニケション手段の中心となり、「ろうベース」でろう学校教育を受けた人は手話がコミュニケーション手段の中心となります。(コミュニケーション手段は、個人の障害の程度や生育歴によって違うので、必ずしもこのとおりではありません。)
盲学校やろう学校で教育を受けたことのない盲ろう者は、手のひらに文字を書いて貰う方法(手書き文字)や、紙に大きな字を書いて筆談するなどのコミュニケーション手段を用いることがあります。
2.コミュニケーション方法の種類と通訳
盲ろう者のコミュニケーション方法は、前述のとおり、視覚及び聴覚の障害の程度や生育歴、他の障害との重複のしかた等によって実に様々です。欧米ではおおむね手話や指文字を原型としたものが多いですが、日本では点字を応用したものも使うなど、特に種類が多いです。従って、通訳・介助者を養成する場合も、個々の盲ろう者に合ったコミュニケーション手段で通訳ができるよう、様々なタイプの通訳・介助者を養成する必要があります。
①触手話
聴覚障害者が使っている手話を基本としています。手話を使う相手の両手に軽く触りながら触読するところから、「触手話」と呼ばれています。弱視の人は近い距離から相手の手話を目で見て理解することもあります。視野の狭い弱視ろうの人と話す場合は、手話の動きを小さめにする必要があります。弱視の人は暗いところが苦手であったり、逆に明るいところではまぶしくて見えなかったり様々なタイプがあるので、その人に合わせた環境を選ばなければなりません。
②指文字
相手の手のひらに、指文字(50音やアルファベットを手の形で表せるようにしたもの)を綴って会話する方法です。受け手は手のひらを軽くすぼめて、指の形が分かるようにしたり、手のひらへの当て方で、文字の形が識別できるようにするなど、若干の工夫が必要です。
③指点字
両手の人差し指、中指、薬指の6本の指を差し出し、これを点字タイプライターのキーに見立てて点字記号を打つ方法です。向かい合わせで会話するときと、横に並んで会話するときでは、点の位置が左右逆になります。どちらのタイプなら理解できるのか、会話を始める前に確かめてから行います。
④ブリスタ通訳
「ブリスタ」はドイツ製の点字タイプライターで、1枚の紙に点字を打つのではなく、幅13ミリの紙テープに点字が1列に打たれて出てくるものです。途中で頻繁に紙を替える必要がないことと、軽量で音が小さく、会議などの通訳に用いられることが多いです。横に並んで1本の紙テープを複数の人で読むこともできます。打たれた点字が本人の指先に送られてくるまでの時間差があるのが難点です。即時性のある指点字と組み合わせれば、スムーズな会議参加を図ることができます。
⑤手書き(手のひら書き)文字
相手の手のひらに指で直接文字を書く方法。特別な技術を身につけなくても、誰にでもできるのが利点です。多くの盲ろう者が理解できますが、かな文字を使う人、カタカナ文字を使う人、漢字も含め、どんな文字でも大丈夫な人、読むのが早い人、遅い人、様々であるので相手に合わせることが大切です。
⑥筆記通訳
弱視ろうの人に有効な方法です。紙に大きな文字で書いて筆談の形で行ないます。会議などの通訳の場合は、大きな紙に沢山書くよりも、小さな紙に少しずつ書いては渡すようにした方が効率的です。文字の大きさ、太さ等は人によって様々なので注意が必要です。多くの人が白地の紙に、黒い色で書くことを好みますが、紙の色、ペンの色、照明など、できるだけその人が読みやすい環境を整える必要があります。
⑦音声通訳
盲難聴の人で、耳元で話せば分かる人の場合、音声通訳をします。耳元で、その人がもっとも聞きやすい大きさの声で、相手の発言をそのまま繰り返して伝えます。雑音の多い環境はあまり快適ではなく、個人的な会話の場合はできるだけ静かな場所を選びます。
⑧パソコン通訳
弱視ろうの人に対して行う通訳方法。机の上のパソコンの画面に大きな文字を写し出して行う方法。1対1で行う場合もありますが、1対多数で利用できるのが利点です。最近、会議などでは、従来の手書きOHPに替わって、パソコンを使って会場のスクリーンに映し出す方法が増えてきているので、そのシステムとつなげば、個々の机の上でも同じ画面を見ることができるようになっています。画面の文字を、自分の見やすいように設定できるのも利点です。
Ⅳ.
1.目的
この事業は、市内に住んでいる又は市内で働いている盲ろう者(視覚および聴覚の両方に障害がある方)に対して、通訳・ガイドヘルパーを派遣することにより、盲ろう者の社会参加を推進することを目的としています。
2.派遣対象者
身体障害者手帳1級および2級の視覚および聴覚の両方に障害がある者又は、
3.派遣対象範囲
官公庁等の公的機関又は医療機関等に赴く場合です。ただし、医療機関については継続的な通院は除きます。また、社会参加の観点から、日常生活上、外出の必要なときに派遣対象としますが、次の場合を除きます。
【対象外となるもの】
・通勤、営業活動等の経済的活動
・通学、通院等の長期にわたる外出
・社会通念上本制度を適用することが適当でないもの
上記以外で、市内で開催される行事等で次に該当するものに対しても派遣します。
・公共団体及び公的機関が主催する会議、大会等
・障害者団体及び福祉関係団体が主催する会議、大会等
・その他、市長が必要と認める会議、大会等
4.派遣費用
通訳・ガイドヘルパーの派遣に係る利用者の費用負担は無料です。ただし、派遣の対象となった盲ろう者が、交通機関を利用して外出する場合、通訳・ガイドヘルパーにかかる交通費等の費用は原則として、盲ろう者が負担することとなります。
5.派遣時間
通訳・ガイドヘルパーの派遣時間は1人につき原則として1日4時間を限度とします。
6.事業の実施団体
7.通訳・ガイドヘルパー
通訳・ガイドヘルパーは、
8.他のコミュニケーション支援事業との違い
手話通訳や要約筆記派遣事業と同等に、派遣に係る個人負担はありません。しかし、社会参加の為の移動を伴う移動支援に係る本人負担は1割であるため、ここに違いがあります。
Ⅴ.盲ろう者支援に関連のある社会資源
(1)
市内に2箇所ある身体障害者福祉センターの一施設です。障害者の社会参加と自立、そして生きがいの創出を目的とした各種講座の開催や、障害者当事者活動やボランティア団体の活動の場として貸館業務を行ないます。同館内では、視聴覚障害者情報センターにて手話通訳、要約筆記、盲ろう者通訳・ガイドヘルパーの派遣を行なっています。社会参加推進センターでは、就労につながるパソコン講座の開催等を開催しています。
〒804−0067
電話:093−883−5555 FAX:093−883−5551
(2)全国盲ろう者協会
この協会は、平成3年に厚生大臣の認可を得て設立されました。協会は、当時はまだ都立大学の大学院生だった福島智さんの勉学を支えるべく組織されていた「福島智君とともに歩む会」にヒントを得、その活動の輪を広げることを目指して設立されました。
〒101−0051
電話:03−3512−5056 FAX:03−3512−5057
(3)盲ろう者支援サークルひまわり
盲ろう者の支援者で構成されてます。活動は月曜日に戸畑区ウェルとばた6階の東部障害者福祉会館にて10:00〜14:00まで活動しています。